【肩こりがつらい女性へ】マッサージでもストレッチでも改善しない…そんな肩こりに必要なアプローチとは?理学療法士が肩こりの改善法を解説!

「エアコンで体が冷えて、肩がつらい…」
「ストレッチはその場しのぎで、すぐに元通り…」
「こめかみが痛くなるほどの頭痛…これ、肩こりが原因かも?」
「パソコン業務が多くて、最近肩こりがひどくて集中できない…」
そんな悩みを抱えて、整体院つなぐにご来院される女性が増えています。
じつはその肩こり、マッサージやストレッチだけでは根本的に改善しません。
理学療法士として25年の経験をもつ院長が、根本から肩こりを改善する方法についてお伝えします。
目次
- 1.肩こりがひどくなる理由|なぜ女性に多い?
- (1)身体的な訴え
- (2)生活への支障
- (3)心理的な訴え・感情面
- (4)よくある背景・生活環境
- 2.マッサージ・ストレッチで良くならないときの本当の原因とは?
- (1)根本の原因1:肩甲骨が動いていない
- (2)根本の原因2:骨盤の傾き → 猫背になる
- (3)根本の原因3:呼吸が浅くなっている
- (4)表面的な施術では、根本的な改善にならない理由
- (5)根本改善には「姿勢・動き・呼吸」を整えること
- 3.デスクワーク女性の肩こりに共通する3つの特徴
- (1)長時間の前かがみ姿勢
- (2)腕・手首の使いすぎ
- (3)ストレスと緊張
- 4.肩こりが引き起こす不調の連鎖とは?
- (1)頭痛(緊張型頭痛)
- (2)目の疲れ・眼精疲労
- (3)集中力の低下
- (4)イライラ・不眠
- 5.『整体院つなぐ』のアプローチ|動かす力を取り戻す
1.肩こりがひどくなる理由|なぜ女性に多い?
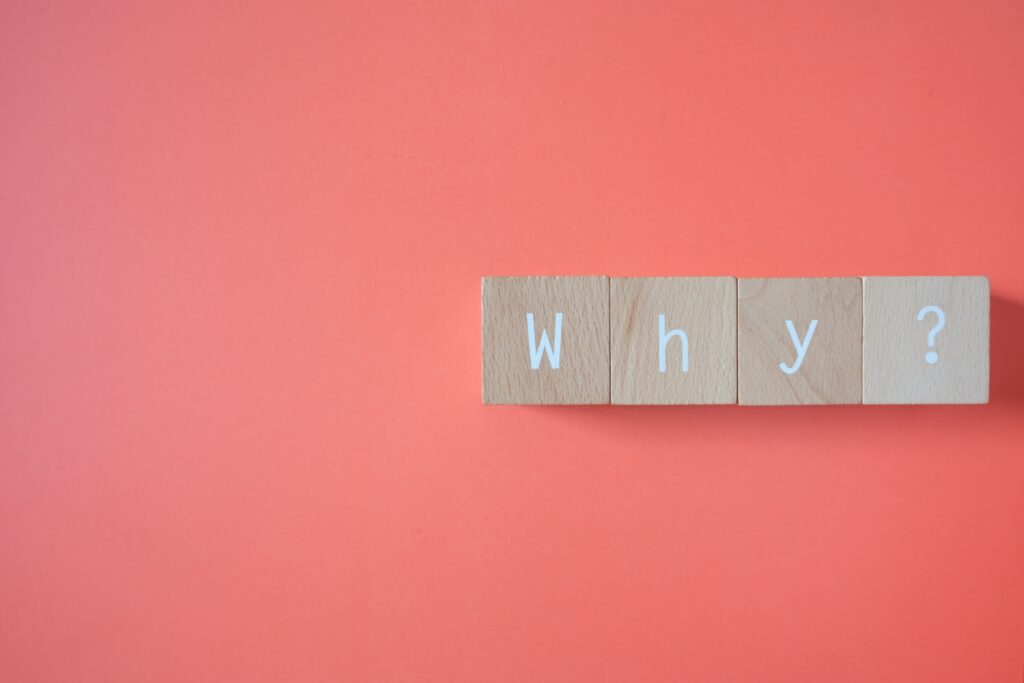
肩こりがひどい女性患者の訴えは、単なる「肩が痛い」ということだけにとどまらず、身体的・精神的・生活的な不調が複雑に絡んでいます。
以下に代表的な訴えを分類してまとめます。
(1)身体的な訴え
- 肩が重くて、いつも鉛のように感じる
- こめかみや後頭部がズキズキする。頭痛薬が手放せない
- ストレッチしてもすぐ戻る
- 肩から背中までパンパンに張っている
- 肩甲骨の内側がいつも痛い
- 腕を上げるとつらい
(2)生活への支障
- 肩こりがひどくて仕事に集中できない
- 朝起きても疲れが取れていない感じがする
- 家事や育児の途中で手が止まるほどつらい
- 肩こりがひどいと、外出する気力もなくなる
- 同じ姿勢が長く続かない
(3)心理的な訴え・感情面
- このまま一生治らないのかもと不安になる
- 病院や整骨院を何ヶ所も回ったけれど、改善しなかった
- 自分だけがこうなる気がして、孤独を感じる
- 周りに理解されなくてつらい
- 常にイライラして、家族にも当たってしまう
(4)よくある背景・生活環境
- デスクワーク中心(座りっぱなし)
- エアコンによる冷え
- スマホ・PC時間が長い(肩が前に巻き込まれている)
- 運動不足
- 忙しくて自分のケアを後回しにしている
女性はホルモンバランスの影響や、感情の変化を身体に抱え込みやすいため、肩こりは単なる筋肉疲労だけでなく、生活・感情・環境が複合的に影響しているケースが多いです。
2.マッサージ・ストレッチで良くならないときの本当の原因とは?

肩こりに悩む方の多くが、
「マッサージしてもらったときは楽になるけど、すぐ戻ってしまう…」
「ストレッチは効いた気がするけど、またすぐに重だるくなる…」
といったお悩みを抱えています。
それには明確な理由があります。
肩こりの本当の原因は、実は肩そのものではないことが多いからです。
悪い姿勢・冷え・ストレスによって、肩に負担が集中してしまい、痛みやこりとして現れているだけなのです。
(1)根本の原因1:肩甲骨が動いていない
デスクワークやスマホの多用により、肩甲骨が固定され、動かなくなっている方が多く見られます。
肩甲骨は肩の土台。ここが動かないと、肩の筋肉は常に緊張しっぱなしになります。
肩甲骨が動かないと、次のような不調が出てきます。
- 肩がすくんだままになる
- 呼吸が浅くなる
- 首や背中の筋肉までガチガチになる
(2)根本の原因2:骨盤の傾き → 猫背になる
長時間の座り作業で、骨盤が後ろに倒れると、背骨は丸まり、猫背になります。
その結果、頭が前に出る「ストレートネック」になり、頭の重さを支えるために肩に過度な負担がかかってしまいます。
<猫背姿勢の連鎖>
骨盤後傾 → 背中が丸まる → 頭が前に出る → 肩が常に緊張 → 肩こり・頭痛
(3)根本の原因3:呼吸が浅くなっている
意外に見落とされがちなのが「呼吸」です。
猫背になると、横隔膜や肋骨の動きが制限され、呼吸が浅くなります。
浅い呼吸は、自律神経を乱し、全身の筋肉に「緊張」の信号を送り続けます。
その結果、肩回りは常にこわばった状態になり、肩こりが慢性化してしまいます。
(4)表面的な施術では、根本的な改善にならない理由
マッサージやストレッチは、あくまで筋肉に直接働きかける一時的な対処法です。
筋肉の緊張を一時的に緩めることはできても、「なぜその筋肉がこっているのか?」という構造的な原因には届きません。
「肩がこっている」のが問題なのではなく、「肩に負担がかかり続けている状態」が問題なのです。
(5)根本改善には「姿勢・動き・呼吸」を整えること
整体院つなぐでは、肩だけを診るのではなく、「全身のバランス」から整えていきます。
- 骨盤と背骨の配列を整える
- 肩甲骨と肋骨の動きを取り戻す
- 深く安定した呼吸を再学習する
こうしたプロセスを通して、ご自身の体が自然に肩こりしなくなる状態を目指します。
3.デスクワーク女性の肩こりに共通する3つの特徴

肩こりに悩んでいるデスクワークの女性はとても多いです。
皆さんに共通している特徴について解説します。
(1)長時間の前かがみ姿勢
長時間のパソコン作業では、無意識のうちに首が前に出て、背中が丸まりやすくなります。
この猫背姿勢は、肩甲骨まわりの筋肉や関節の動きをロックしてしまい、肩の可動域を大きく制限してしまいます。
その結果、肩まわりの筋肉が常に緊張したままとなり、血行不良と疲労物質の蓄積が起こりやすく、慢性的な肩こりにつながっていきます。
(2)腕・手首の使いすぎ
マウスやキーボードの操作は、腕や手首の細かい動きの繰り返しです。
実はこの動きは、直接は使っていない「肩」にも影響を与えます。
というのも、腕や手首を支えているのは肩の筋肉だからです。
たとえば長時間カバンを持っていると肩が疲れるのと同じように、パソコン操作も間接的に肩へ負担をかけ続けているのです。
(3)ストレスと緊張
仕事のプレッシャーや人間関係のストレスは、知らず知らずのうちに身体を緊張させます。
特に肩や首は「力み」を感じやすい部位。
ストレスが蓄積すると、自律神経が乱れ、筋肉の緊張が慢性化してしまいます。
さらに呼吸も浅くなり、酸素供給が不十分になることで、筋肉がこわばりやすくなる悪循環が生まれます。
つまり、肩こりの原因は肩そのものではなく、姿勢・使い方・ストレスなど、身体全体のバランスの崩れにあります。
だからこそ、マッサージやストレッチだけでは根本的な改善につながらず、すぐに元に戻ってしまうのです。
4.肩こりが引き起こす不調の連鎖とは?

長時間のデスクワークやストレスによって肩や首まわりの筋肉が緊張し続けると、肩まわりの筋肉が硬くなり、その部位の血行が悪化します。
血行が悪くなると、筋肉に十分な酸素や栄養が届かなくなり、それと同時に、老廃物が排出されにくくなるという悪循環に陥ります。
肩や首の筋肉と頭部は、血管・神経を通して密接につながっています。
筋肉の硬直によって周辺の血管が圧迫されると、脳への血流も滞りがちになります。
酸素不足と老廃物の蓄積は、脳へ悪影響を及ぼします。
その結果、次のような症状が出てくるのです。
(1)頭痛(緊張型頭痛)
筋肉の緊張が続くことで、後頭部やこめかみが締めつけられるような痛みに。
「頭が重い」「ずっと圧迫されている感じがする」などの自覚症状が増えます。
(2)目の疲れ・眼精疲労
首・肩の血行不良が原因で、目の周りの筋肉にも十分な酸素が届かず、目のピント調節やまばたきの機能が低下します。
(3)集中力の低下
脳への酸素供給が不十分になると、「ぼーっとする」「ミスが増える」といった注意力や集中力の低下が顕著になります。
(4)イライラ・不眠
血流や神経伝達が悪くなることで、自律神経が乱れ、気分が不安定に。
眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりする人も少なくありません。
肩こりは単なる筋肉の問題ではなく、脳や神経にまで影響を及ぼす全身の不調のはじまりなのです。
たかが肩こりと軽く見ず、早めのケアが大切です。
5.『整体院つなぐ』のアプローチ|動かす力を取り戻す

肩を揉むのではなく、肩に負担をかけている根本原因から整えていく。
それが、理学療法士として25年の経験をもつ私たち『整体院つなぐ』のスタンスです。
当院では、ただ痛みを取るのではなく、「なぜその痛みが生まれたのか?」を、動き・姿勢・呼吸・生活習慣まで掘り下げて見ていきます。
さらに理学療法士として培ってきた運動学の知見から、
- 骨盤の傾きや猫背など全身のバランスの崩れを調整
- 固まった肩甲骨や肋骨の可動性を回復
- 浅くなった呼吸を深くゆるめる呼吸法にリセット
といった根本的な回復を目指します。
「もう仕方ない…」とあきらめていた肩こりでも、あなたの体に眠っている治る力は、必ずあります。
まずはお話を聞かせてください。
『整体院つなぐ』は、患者様のいまを支える力になります。
理学療法士は、運動学や解剖学の専門知識を活かし、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、適切な運動療法を提案します。
肩こりの原因を特定し、根本的な改善を目指すことで、患者さんの生活の質を高めることができます。
一人ひとり、肩こりの原因は異なります。
必ず専門家に相談し、ご自身に合った改善をめざしましょう。













